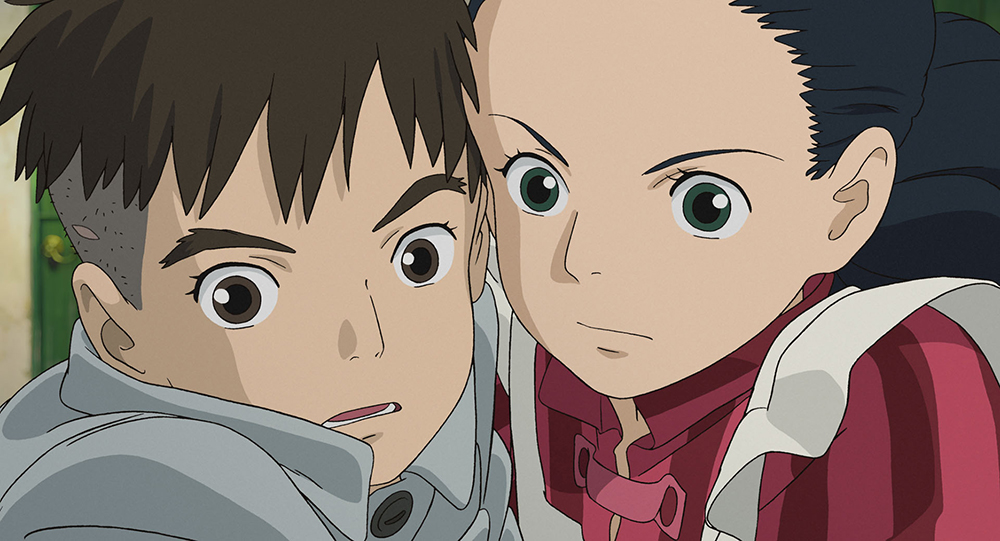国際交流基金主催の「インド日本映画祭」は今年9月にインドの首都デリーで幕を開け、来年2月16日まで7都市を巡回し、日本映画の最新作など25作品を上映する。そんな大規模な日本映画祭でオープニングを飾ったのは、現在日本でも大ヒット中のアニメ映画『天気の子』だ。新海誠監督はインドでの初上映となった9月27日、舞台挨拶に登壇し、地元のファンと交流。インドのファンが始めた署名活動がきっかけとなり、同作は日本のオリジナルアニメ映画として初となるインドでの劇場公開に漕ぎ着けたという経緯がある。新海監督が、そんな特別な繋がりによって実現したインドでの上映について振り返った。

――インドでの『天気の子』プレミア上映、大変な熱狂ぶりでした。インドの観客の印象はいかがでしょうか。
新海:すごくピュアで可愛らしい反応だなと思いました。可愛らしいというか、愛おしいという感覚ですね。彼らは自分が面白いと思うことを「面白い」と言うことにてらいがなく、最初から楽しもうという意識で前のめりで来てくれます。もしかしたら国民性のようなものかもしれませんが、日本とは随分違うなと思いました。日本でもそういう方はたくさんいらっしゃいますし、年々増えている気もしていますが、一方で映画を批評的に観る方もたくさんいます。あるいは、自分が面白いと思うことを「面白い」と言っていいかどうか迷いがあったり、一度周りを見渡してから自分の態度を決めていく雰囲気もあり、映画のレビューサイトなどを見ていてもそう感じることがあります。
一方でインドの方々は、もともと私の映画について知らない方もいらっしゃったはずですが、知っているかどうかに関わらず全力で映画を楽しみにきており、(上映自体が)作品と観客との共同作業、いわばコラボレーションのような空間になっていて、感動的でした。

――インドでの『天気の子』の劇場公開を求める署名活動は、インドの高校生パンチョーリくんが署名サイト「Change.org」で始めました。この署名運動をどのようにお知りになったのでしょうか?
新海:ツイッターで僕のアカウントに、インドの方から「インドで署名を始めているので、サポートしてください」という英語のメッセージが来たんです。「change.org」はそんなに怪しいサイトではないですし、その時点で確認したところ、すでに1万人ほどが署名を行なっていました。基本的に僕はファンからのメッセージに対して、日本的な感覚だと不公平になってしまうので返事をしないようにしているのですが、万単位で署名が集まっているんだったらメッセージを投げておこうと思い、インドで公開できるかわからないけれど、皆さんの気持ちは本当に嬉しいので、配給会社の方にぜひ伝えておきます、という内容のツイートをしたんです。そうしたら、そこから後の僕のツイッターのリプライはインド人からで埋まってしまって(笑)。ものすごくいっぱい来ました。お願いだから来てください、というメッセージで溢れていて。その行動そのものをすごく愛おしいなと思いましたし、そうするうちに署名も5万人を超え、東宝からもインドの配給会社が決まりましたと。そこに、国際交流基金の方々との良いタイミングでのマッチがあり、インドでの上映が実現しました。そのことによって日本のファンも「インドで公開できるんですか!?」と喜んでくれました。
――では最後に、インドの観客への思いをお聞かせください。
新海:自分が人生で訪れたことのなかった国に、自分の映画を好きな人がこんなに存在することを、これでもかというくらい目の当たりにさせられて、すごく勇気づけられましたし、「こういうことのために僕たちは映画を作っているんだ」という気持ちになりました。昨日の夜、ホテルでうちの会社(コミックス・ウェーブ・フィルム)の川口(典孝)社長と少しウイスキーを飲みながら、「本当にやってきてよかったよね」「作品を作ってきて、作品を届けるっていうのはこういうことなんだね」という話をしました。僕も同じ気持ちでした。こんなに楽しんでもらえるんだったら、次もやっぱりインドに作品を持ってきたいです。作品作りにおいては、日本の観客に特化すると言いましたが、その気持ちは次の作品でも変わりません。それでも、インドの人たちに楽しんでもらうためにもう少し分かりやすくするにはどうしたらいいかということを、彼らの熱意に触れたことで考え始めています。とにかくドメスティックにやろうと思ってきましたが、それだけじゃなくもう少しだけ外側のことも視野に入れながらアニメーション映画を作っていけば、彼らも喜んでくれるかな、喜ばせたいな、と思っています。
ボリウッドと呼ばれるほどに自国の映画産業が盛んなインド。それだけに、日本映画が一般公開されること自体が異例のことで、ましてやインドで子どもが観るものとしての認識が強いアニメ作品ならなおさら、そのハードルが高かったことは想像に難くない。それでもこうして上映が実現したことに、映画の持つ力を改めて実感させられた。
取材:許斐雅文 / 編集:いしがみえみ