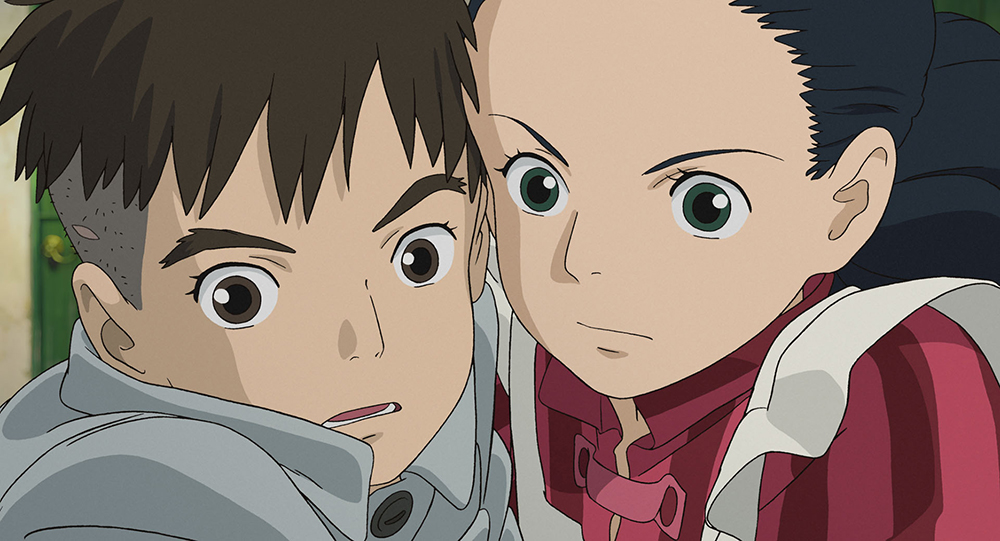新海誠監督の『すずめの戸締まり』がグローバルな市場で大きな成果を上げた。海外動員は3,500万人を超え、海外興行収入は280億円を突破。特にアジアでの勢いが凄まじく、中国や韓国では日本映画の歴代記録を塗り替えた。
新海監督は『すずめの戸締まり』プロモーションで2023年2月から中国、インド、タイ、メキシコなど海外9カ国13都市を訪れた。本記事ではその新海監督が海外を訪れた経験と、そこで抱いた実感を語ってもらった。
東日本大震災を題材に選んだ『すずめの戸締まり』は、日本人の目からは新海作品のなかでも日本の文化や歴史の理解を必要とする物語に映る。そういった文脈のギャップを越えて本作が海外でもヒットした要因を、新海監督は「日本のアニメが新しいフェーズに入ったから」と分析している。一体どういうことなのか。
取材・文:嘉島唯 写真:黒羽政士 編集:久野剛士・森谷美穂(CINRA, Inc.)
新しいフェーズへ突入した、海外における日本のアニメ作品事情
——『すずめの戸締まり』(2022)のヒットをふまえ、新海監督は「日本のアニメーションの世界興行が別のフェーズに入った」とツイートされていました。これまでと何が違いましたか?
新海:『すずめの戸締まり』は、日本国内よりも海外での興行収入の方が大きくなりました。
それを実現させてくれたのは各国の配給会社さんの力が大きいです。優れた映画さえつくれば世界でヒットするわけではなく、作品を届ける努力も必要不可欠です。僕らは映画をつくり始めた頃から新作を公開するたびに海外での映画プロモーションを続けてきましたが、今回は特に配給会社さんたちの熱意とプロモーションの規模が違っていた。それを、2月から約3か月かけて海外を回る中で大いに実感しました。

——各国の期待値が高かったということでしょうか?
新海:そうですね。そしてそれは、「新海作品だから」というよりも、日本のアニメ作品自体への期待のように感じました。
海外のお客さんは僕の作品だけでなく、ほかにも好きなアニメ作品がたくさんあるようでした。『呪術廻戦』や『ONE PIECE』のような『週刊少年ジャンプ』原作のアニメも好きで、『すずめの戸締まり』より少し後に公開された『THE FIRST SLAM DUNK』も、各国でヒットしていますよね。
配給会社からは「コロナ禍によって、自宅で映像配信を視聴する文化が一般化したことが大きい」と聞きました。
もちろんいままでもアニメファンは世界中に大勢いましたが、日本のアニメというものがコロナ禍のタイミングで世界に発見されたと言えるのかもしれません。そして、日本のアニメの観客層が従来のファン層よりも広がったタイミングで『すずめの戸締まり』が封切られたことで、今回の結果がもたらされたのだと思います。
新海監督の背中を押した、あるシリア人女性の言葉
——新海監督の作品は、日本での暮らしの細やかな描写が評価されていると思います。海外でも日本独特の描写は伝わるのでしょうか?
新海:僕は、基本的には日本の観客に向けて映画をつくっているのですが、そういった日本文化の「前提」をふまえた描写は、海外の方にはニュアンスが伝わらないのではないか、という不安を抱いていた時期もあります。
例えば、『秒速5センチメートル』(2007)での電車が遅れて焦るといった描写に対して「電車は遅れるものでしょ」と思う国の人もいるだろうし、春に桜が咲くことの情緒は、桜の樹がない地域の方には想像するのが難しいですよね。
新海:そういう、これで伝わるのだろうか、伝わらなかったら申し訳ないなという思いを当時は海外で公開するたびに感じていて。だったら、ファンタジーの冒険物語ならば国籍を問わずいろいろな人に楽しんでもらえるのではないかと、『秒速5センチメートル』の次はファンタジー要素の強い『星を追う子ども』(2011)をつくりました。だけど、一定の評価をいただいた一方で「あなたに期待しているのはそうじゃない」という声も随分と聞こえました。
——海外でも日本独特の描写のほうが好まれたんですね。
新海:『秒速5センチメートル』の公開時の話題に戻るのですが、シリアのダマスカスで上映した際、年配の女性が「物語が心に深く残り、感動した」と僕に伝えてくれたことがありました。先ほど言ったように、当時は不安が大きかったので、その言葉に嬉しさはありつつも戸惑いもありました。「何十歳も年上のシリアの女性が、自分の個人的な感覚を表現した作品に共感してくれることなんてことがあるのか」と。振り返ってみると、風習も文化も年齢も違う人に物語を通じてコネクトできることを、言葉で初めて教えてもらった経験でした。
そして、『星を追う子ども』の次に『言の葉の庭』(2013)という映画をつくりました。「日本庭園で万葉集を読む」というかなり日本的な作品になったのですが、海外の上映でとても評判が良かったんです。上映した国では梅雨のない地域もあるだろうし、舞台となる東京という場所に縁のない人も多かったと思いますが、そういう前提を知らなくても「この作品が1番好き」と言ってくれた人がたくさんいました。
新海:海外での『言の葉の庭』の反響から、シリア人の女性の方が言ってくれたことがようやく実感を伴ってわかりました。「自分たちの足元を掘るような作品をつくったとしても、海外でも楽しんでくれる人がいるんだ」と。お客さんに背中を押されることで、こういう方向でもいいのかもしれないと、自分の道筋が見えたように思えました。そして、そこから『君の名は。』(2016)という作品をつくり、さらに国内外での観客が増え、いまに繋がっています。
『すずめの戸締まり』海外上映を通じて得た、エモーショナルな体験
——わが道を進むにあたって、海外の方からの声もパワーになったのですね。そのパワーによって意識が変化したこと・再認識されたことはありますか?
新海:いまもグローバルを意識するよりも「足元をしっかり描きたい」と思っています。「海外で日本の作品の魅力が伝わるか」というテーマで考えると、そもそも観客ごとに知識や経験、価値観などは違うので、結局のところそれは個々人による、としか言えないですよね。だから僕は、前提となる知識に差があると認識したうえで、より多くの人が楽しめるように物語をつくろうとしています。
ただ、『すずめの戸締まり』は東日本大震災を扱っているので、海外の観客には作品に込められた意味を100%理解してもらうのは難しいような気がしていました。
新海:そこで、海外の舞台挨拶では必ず「東日本大震災のことをどれぐらい知ってますか?」と質問をしてきました。大体どの国も3割ぐらいの観客が手を挙げます。なかにはアメリカの海兵隊員で「トモダチ作戦」として被災地の救援活動に従事していた方もいました。ただし7割の観客は東日本大震災を知らない。ほとんどの人が楽しいエンタメを観ようという気持ちで映画館に来てくれていました。
海外での舞台挨拶はどこもすごく賑やかです。ときにはお客さんが壇上に上がって一緒にセルフィーを撮るぐらい熱烈に歓迎してくれる。でも、「この作品は、東日本大震災という日本で実際に起きた災害をベースにつくっている」と話をすると、劇場が息を飲んだように静かになるんです。

新海:「映画のなかで描かれている、建物の上に乗っかった船や燃える街の風景は、12年前の日本で実際にあったもの。鈴芽のような境遇の人が当時の日本には大勢いた」と続けると、会場はより一層静まり返ります。
メキシコでは作中の「黄色い蝶」の話をしました。「ヒロイン・鈴芽の近くにときどき現れる蝶は、鈴芽の母への想いなんです」といった話をすると、みなさん涙を流してくれました。通訳の方も声をつまらせていて、僕にとってもすごくエモーショナルで素晴らしい体験になりました。
7割の方が東日本大震災を知らないけれど、それでも作品をエンタメとして楽しんでくれた。上映をきっかけにして日本で起きた出来事を海外の方々に知ってもらえた。それだけでも、『すずめの戸締まり』を海外に届けられてよかったなと思います。

——東日本大震災という枠を超えて「災害の物語」として共感する人も多そうです。
新海:海外での上映を通じて、印象深かったエピソードがたくさんあります。例えば中国のファンからは「2008年に起きた四川大地震を思い出させる映画で、救いのメッセージを受け取った」という長いお手紙をいただきました。インドでは「幼い頃に母を亡くした鈴芽の悲しみと、コロナ禍で身近な人を亡くした悲しみが重なって泣いてしまった」という言葉もありました。
普遍的な作品をつくる、新海監督のアニミズムのような感性
——なぜ国を超えて物語が届いたのだと思いますか? 物語を届けるうえで重視していることはありますか?
新海:僕は、グローバルなものを最初から目指しているわけではなく、自分自身が感じる実感を手がかりに映画をつくっています。
例えば、僕は子どもの頃、野山に囲まれた長野の田舎に住んでいて、長野には八ヶ岳という山があるのですが、それがときどき大きなクジラのように見えたことがありました。『すずめの戸締まり』で言えば、山肌に巨大な「ミミズ」が立ち上がる描写は実際に見たことはないけれど、僕は子どもの頃から知っているような気がする。

——アニミズムのような感覚ですね。
新海:だけど、そうした感覚はきっと国籍に関係なく、誰しもに備わっている感性だと思うんです。そういう、「なんとなくわかるよね」という感覚や、人がなにかに感動したり気持ちを掻き立てられたりする瞬間は、それぞれの人々が持っている文化的背景によって具体的な感じ方は違うでしょうけれど、根本的なところでは日本でも海外でもそんなに大きくは違わないはずですよね。そのことは、僕だけではなくきっと多くの人が感じている実感だと思います。そうやって、自分の足元にある地面をずっと掘っていけば、地球の反対側まで穴が通じるかもしれない、と思いながらつくっています。
「やっとスタート地点に立てた」新海監督が感じた日本アニメの現在地
——冒頭でお話した「新たなフェーズ」のなかで、日本のアニメ作品は今後どうなっていくと思いますか?
新海:国際的なマーケットの中では、日本のアニメ作品の存在感はもっと大きくなっていくと思います。ビジネスの視点だけで考えれば、アニメに限りませんが、国内だけで収益を賄おうとするのはすでに難しくなっています。日本のゲームは随分前から海外マーケットに移っていて、日本のアニメーションも同じような流れが生まれ始めていると思います。
ただ『ベルリン国際映画祭』に参加して、アニメ作品が国際的な映画祭のような場で、映画として評価を受け存在感を増すにはまだ時間がかかるのではと思いました。例外的に宮崎駿さんのような突出した方もいらっしゃいますし、映画祭で素晴らしい実績を残す日本の作品もありますが、そうではない僕たちのような立場の作り手にとっては、ようやく日本のアニメがスタート地点に立った段階なのかなと感じました。

新海:僕個人としては、より多くの観客に届けることが楽しみなので、映画祭といった賞レースにかけるモチベーションはあまり高くはありません。一方で、多くの観客に届けるために、国際的な映画祭が影響力を発揮する場合もあります。 だから「多くの観客に届けたいなら、賞レースも大切にしたほうがいいのかもしれない」と自分を奮い立たせてもいます。
——ヒットという山を登ったら、また別の山を見つけたのでしょうか。
新海:山を越えたり登ったりすることだけが目標というわけでもないのですが、いろいろな場所をめぐったおかげで海外での日本のアニメの受容のされ方や見えなかった光景を垣間見ることはできました。そういう意味でも『すずめの戸締まり』をつくってよかったと思います。
——『すずめの戸締まり』は、『天気の子』(2019)の舞台挨拶で日本各地を回ったことでロードムービーの構成になったそうですが、次の作品の舞台は海外になる可能性もありますか?
新海:ありがたいことに、どこの国でも同じ質問を聞かれます。そのうえで「次はうちの国を舞台にして欲しい」ともお願いされます(笑)。
そう言っていただけるのはとても嬉しいですし、作品世界をもう少し広げたいと思ったり、自分が見てこなかった風景を映画にしたいという欲望もあったりするので、いつかは自分が住んでいるのとは違う国、異なる時代を舞台に物語を描く日が来るかもしれませんね。ただ、次回作についてはまだ具体的に考えていないのでなにもわからないですけど(笑)。
新海誠
1973年生まれ、長野県出身。アニメーション監督。『秒速5センチメートル』(2007)、『君の名は。』(2016)、『天気の子』(2019)などの作品が国内外で高い評価を受ける。最新作『すずめの戸締まり』は世界で興行収入460億円を突破した。