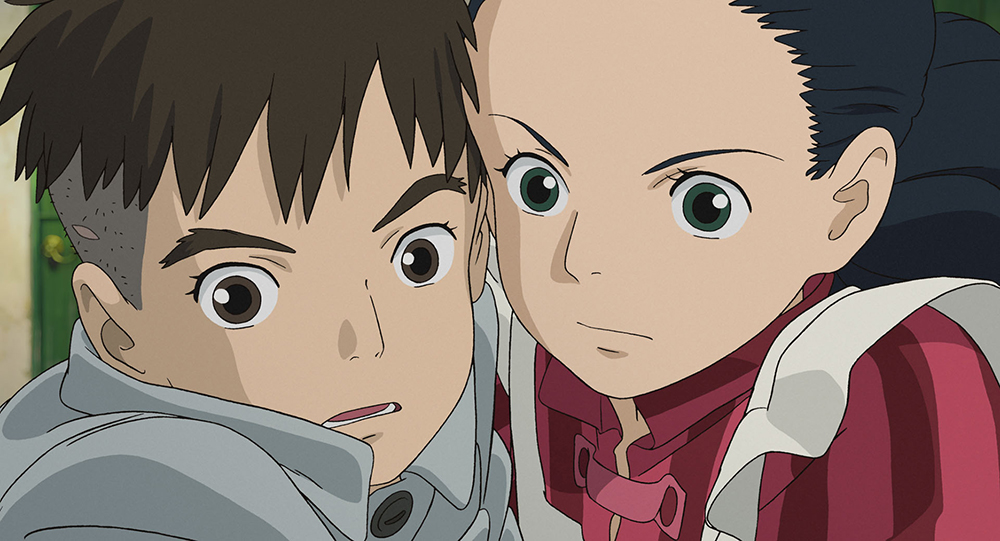人間のダメな部分、あるいは誰もが隠したいと思う人間の恥部を、ダークなユーモアとともに描かせたら右に出る者はいない——『机のなかみ』(2006)で本格的な監督デビューを果たして以降、最近作『神は見返りを求める』(2022)に至るまで、ある種一貫した作風で人気と評価を高めてきた𠮷田恵輔監督。世界各国で開催される「JFF(日本映画祭)」のラインナップにも、『BLUE/ブルー』(2021)と『空白』(2021)の2本が同時選出されている。
今後ますます熱い注目を浴びていくであろう𠮷田監督に、照明部としてスタートしたという意外なキャリアや、自作に寄せる思いについて、あらためて話を聞いた。
取材・文:麦倉正樹 撮影:砂田耕希 編集:井戸沼紀美(CINRA, Inc.)
塚本晋也監督のもとで、幼少期から憧れていた映画の仕事を学ぶ
——𠮷田監督は、『鉄男』(1989)などで世界的に知られている塚本晋也監督のもとで、キャリアをスタートさせたんですよね。
𠮷田:もともと幼稚園ぐらいのときからジャッキー・チェンの映画が好きで、「将来は映画監督になりたい!」と言っているような子どもでした。ハリウッドの大作映画なんかも好きだったんですが、10代のころ、塚本監督の『鉄男』に出会って……。「この映画が、世界でいちばんカッコいいぞ!」って思ったんです。それで、すっかり監督のファンになりました。

𠮷田:「塚本組」は当時、毎回撮影のたびにボランティアスタッフを募集していたんです。塚本監督はカリスマ的な存在だったから、たくさんの応募者がいたんですけど。映画の専門学校に通っていた自分は、なんとかそれをくぐり抜けて、塚本組のスタッフになって。
——そこで照明を担当されていたんですよね?
𠮷田:そうなんです。塚本監督は美術に凝るので、現場に行かない準備班のスタッフも多いんですけど、俺はやっぱり現場に行きたくて。「機材のレンタルとか返却も、俺が全部やります」「車も自分で持ち込むし、全部運転します」と言って、照明スタッフとして、うまいこと現場に立ち会えるようになりました。
——塚本監督の、どのあたりの作品から関わっていたのでしょう?
𠮷田:いちばん最初は『バレット・バレエ』(1999)でした。塚本組って、ひとつの現場が長いんですよ。当時は1作の撮影に8か月くらいかけていましたし、そこから海外の映画祭とかもまわるので、次の作品に取りかかるまでに結構時間があって。
だから俺は作品と作品のあいだに、アルバイトをしながら自分の自主映画をつくっていました。塚本組の映画で最後に関わったのは『悪夢探偵』(2007)なんですが、その撮影の最中にクランクインしたのが『机のなかみ』です。
ずっと好きだったダークなユーモアが、ある日個性に
——『机のなかみ』は𠮷田監督の商業デビュー作になるわけですが、塚本監督のアヴァンギャルドなテイストとはまったく違う、独特な空気感のラブコメディーですよね。
𠮷田:そうですね(笑)。『机のなかみ』を撮る前は、塚本監督の影響を受けた自主映画を10年ぐらい撮っていたんです。でも、いろいろなコンテストに出しても全然引っかからなくて。それで、ある程度時間が経ってから、いくら好きでも、向き不向きがあると気づいたんです。
それと同じころ、塚本組の先輩が「お前は、毎年俺に送ってくる年賀状みたいな映画をつくったほうがいいんじゃないか」って言ってきて。

——「年賀状」ですか?
𠮷田:当時は毎年、先輩たちに年賀状を送っていたんですけど、それが結構ダークな内容だったんです。例えば、全財産を競馬で失ったおじいさんが死を考える暗い4コマ漫画を描いたりして……それと一緒に「あけましておめでとうございます」みたいな(笑)。
そういうひねくれたジョークみたいなものを、ふだんから先輩たちには披露していたので、「もっとそのセンスやユーモアを出したほうがいいんじゃない?」とアドバイスを受けて。それで、『なま夏』(2006)を構想し始めました。
誰かの真似をしたり、他人の評価を気にしたりすることなく、自分が本当に好きなものをつくったので、自己満足的な部分もあったと思います。だけど、塚本組でいろいろ学んだり、評価されなくても自主映画を10年撮り続けてきたりしたおかげで、気づいたら映画的な技術と経験値は着実に増していて。そこで初めて、妙なエンターテイメント性が生まれたんです。要は、他人に見せられるマスターベーションになっていたという。
——(笑)。
𠮷田:面白いもので、自分の欲を突きつめたものがやがて「個性」と呼ばれるものになるんですよ。もちろん、それまでもいろいろ書いてはいたんですが、どこかツギハギみたいなイメージで、何かを生み出している感じが全然しなかったんです。
なのに、「ほかの人はどう思おうと、俺はこれが好きなんだ」と言えるようになってからは、ある日突然自転車に乗れるような感覚で、脚本が書けるようになりました。芝居やカメラ割りに関しても、自分の好みがすごく明確にわかるようになって。それで、ちょっと注目されたり、評価されたりするようにもなってきました。

——それはいつごろですか?
𠮷田:『なま夏』と『机のなかみ』のあいだに『メリちん』(2006)という自主映画を撮ったころですかね。それぐらいから「どうでもいいことで罵り合っている器の小さい人たちが、俺はすごく好きなんだ」っていうことにも気がついて(笑)。
脚本で、人間のカッコいいところを書くのは難しいけど、人間の恥ずかしい部分を投影するときは、すごく筆が乗るなあと。
——人間の「裏の部分」を描くようになってから評価されるようになったというのは、ちょっと面白いですよね。
𠮷田:結局、お客さんにも他人には言えないような人間らしさがあるということだったんでしょう。「わざわざそれを大画面で見なくていい」という声は、映画をつくりはじめた当時からありましたけど(笑)。ただ、ある種、痛快な感じがする部分もあるんだと思います。

「登場人物の短所と長所を同じ配分で描きたい」
——𠮷田監督の映画は「器の小ささ」を揶揄するだけではなく、それもひっくるめて人間を肯定しているようなところがありますよね。
𠮷田:そうですね。人は醜くて愚かなんだけど、それも含めて、何か愛おしいよねっていう感覚は、最初からずっと持っています。ぼくは映画で、一貫して「愛」を描いているつもりなんですよね。
ひと言で「愛」といっても、いろいろなかたちがあると思うんです。好きな人に寄せる愛はもちろん、親子の愛だったり、友情みたいなものだったり……。人でないものに対しての愛もあります。それらをひっくるめた「愛」を、最終的に描きたいというのは、映画を撮り始めたころからずっと思っていて。
厳しい現実だけを並べて、「世の中、こんなにも残酷だぜ」と言うよりも、「世の中は残酷だけど、どこかに光はあるんじゃないか?」という気持ちが、ずっとあるんですよね。
——『空白』は、まさにそういう話でした。
𠮷田:最悪の展開になればなるほど、小さな光にありがたみを感じる感覚を大切にしているというか。まあ、そういう映画を何本もつくっているうちに、だんだん感覚が麻痺してきて、主人公がどんどんつらい目に遭うようになってきているようなところもあるんですけど(笑)。
——それも含めて、𠮷田監督は、いじわるなのか、やさしいのか、よくわからないところがあります。
𠮷田:多分、両方なんだと思います。「君には醜いところがあるよね」と思いながら人間を観察することもあるんですが、同時に「人間ってそういうものだよね」と俯瞰している感覚もあって。
映画づくりでいえば、登場人物の短所と長所を同じ配分で描きたいという思いがあります。いい人がずっといい人のままでいると、ちょっと違和感を感じてしまって。
——𠮷田監督の映画は、登場人物たちに対する目線が、いつもすごくフラットですよね。主人公だけを贔屓しないというか。
𠮷田:『BLUE/ブルー』なんかは、変な話、登場人物のなかの誰が主役でもいいと思っていたんです。3人のボクサーが登場しますけど、脚本の配分もじつはまったく一緒なので。だから、キャスティングによっては、違う人がポスターの真ん中になっていたかもしれない(笑)。
アート映画と娯楽映画の狭間で、つくりたいものをつくる
——そんな𠮷田監督の映画が、このたび世界各国で開催される「JFF(日本映画祭)」で上映されているわけですが。監督は、「日本以外での評価」を、どのようにとらえているのでしょう?
𠮷田:海外での評価については、自分では正直、いまひとつわからないところがあって。芸術性の高い作風に振り切っているような作品であれば、海外の映画祭をまわるのが一般的だと思うんです。けど、俺の映画の場合、国際映画祭に出しても、観客が戸惑うんじゃないかと想像していて。というのも、自分の映画は娯楽映画にもアート映画にも全振りしていない、微妙なポジションだなと。
だから自分の映画がどういうふうに広がるか予測できないところもあるんですが、海外の人たちの率直な感想をもっと聞いてみたいと思っています。

——なるほど。
𠮷田:今回は「JFF」で『BLUE/ブルー』と『空白』の2本が選ばれて……それはすごく光栄なことだと思います。だけど同時に自分のなかでは、その前の『愛しのアイリーン』(2018)とか『ヒメアノ~ル』(2016)とか、あの時代からずっと同じようなものをつくっている感覚もあるんです。
去年の『東京国際映画祭』で初めて特集上映を組んでもらったことも含めて、近年急に注目されるようになってきた感じがあるんですけど、俺はずっと同じことしかしていないんです。正直に言えば、作品のクオリティー的にも、大して変わらない気がするんですよね。だから、これをきっかけに、過去の作品もさかのぼって見てもらえたら、すごくうれしいです。

「日本映画祭(JFF)」開催スケジュール
<カンボジア>
第8回カンボジア日本映画祭
2022年12月2日~2023年2月5日
<フィリピン>
日本映画祭
2023年1月20日~2023年2月22日
𠮷田恵輔(よしだ けいすけ)
1975年生まれ、埼玉県出身。専門学校在学中から自主映画を制作し、塚本晋也監督作品の照明を担当する。2006年に映画『なま夏』で『ゆうばり国際ファンタスティック映画祭』ファンタスティック・オフシアター・コンペティション部門のグランプリを受賞。近作に『ヒメアノ~ル』(2016)、『愛しのアイリーン』(2018)、『BLUE/ブルー』(2021)、『空白』(2021)、『神は見返りを求める』(2022)など。