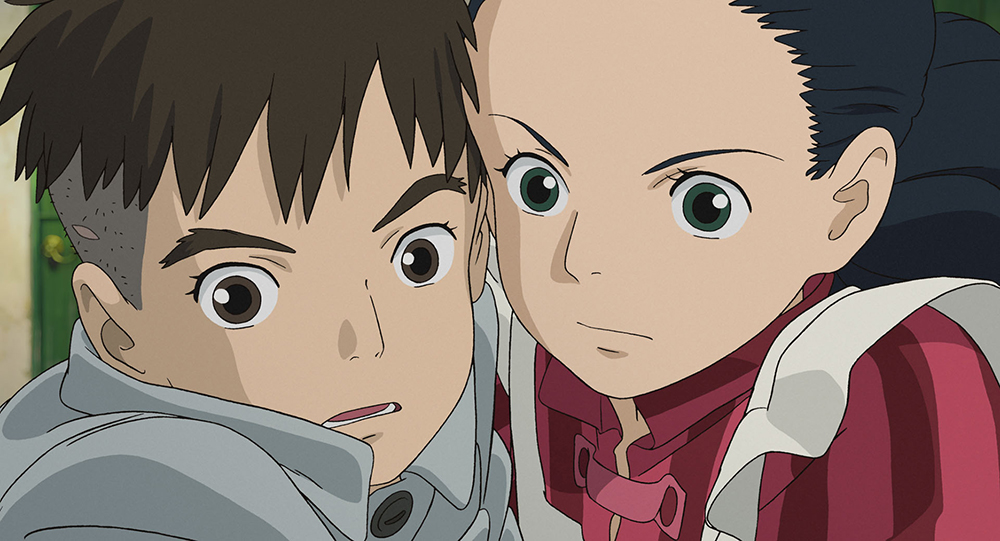日本映画のジャンルごとに、その楽しみ方を紹介する連載シリーズ「日本映画入門」。第3回目のテーマは、日本のアウトロー「ヤクザ」を描いた映画群。クエンティン・タランティーノら、世界の有名映画監督からも愛される娯楽映画の1ジャンルになっている「ヤクザ映画」について、前編・後編の2回にわけてお届けする。
ルーツを遡れば戦前からはじまり、『仁義なき戦い』(1973年)や北野武監督作品、そして2021年にNetflixで全世界配信された『ヤクザと家族』まで、一口に「ヤクザ映画」といっても作品の特徴はさまざま。時代とともに、ヤクザ映画はその姿を変えてきた。その変化の背景にあるのは、映画を巡る状況や、現実社会における「ヤクザ」の立場の変化である。
日本映画史に詳しい映画ライターの轟夕起夫と森直人が、ヤクザ映画の歴史とともに、日本の社会の動きを辿る。前半では、ヤクザ映画のルーツから、深作欣二監督の名作『仁義なき戦い』(1973年)までの時代を紹介する。
取材・文:森直人 編集:久野剛士・原里実(CINRA, Inc.)メインカット:岡田成生

時代劇からはじまる、「ヤクザ映画」のルーツ
轟:「ヤクザ映画とは何か?」――とひと口にいっても、この問いは非常に大きなテーマですよね。
まず、戦後の「日本映画全盛期」とされる1950年代から60年代にかけて、それから興行的苦戦を強いられてゆく70年代までは、大手の映画会社(松竹、東宝、大映、東映、新東宝、日活)は猛烈な量産体制だったわけです。新東宝は1961年、大映は1971年に倒産してしまいましたが……ともかく、その6社が製作から配給、公開まで自社で一手に担っていた商業映画群、つまりプログラムピクチャーの1ジャンルとして、アウトローを主人公とした「ヤクザ映画」が生まれたと。ざっくり定義づけるならば、この認識で良いかと思います。
森:ジャンル映画としていちばん狭義に捉えるなら、1960年代に生まれた東映の「任侠映画(任侠とは、ヤクザとほぼ同義でも使われるが、本来は弱きを助け強きをくじく自己犠牲的な気風を指す)」が起点になるでしょうね。具体的には鶴田浩二主演、沢島忠監督の『人生劇場 飛車角』(1963年)から「任侠映画」という呼称が一般化していったという定説があります。ただそのルーツを探るのであれば、もっと過去に遡らなくてはならない。
轟:任侠映画の起源をたどると、1870年代後半頃までの前近代の日本を舞台にした「時代劇」に行き着きます。例えば、「渡世人」と呼ばれる社会からはぐれてしまった流れ者を描く「股旅物」や、権力や体制への反抗者たちを描く映画の歴史はすでに戦前からあるんです。
ただアウトローの登場する日本映画を、すべて「ヤクザ映画」の範疇に入れてしまうのは当然難しい。例えば黒澤明監督の『酔いどれ天使』(1948年 / 東宝)だって、三船敏郎が戦争直後の闇市を仕切るヤクザを演じています。まあ、黒澤自身は「ヤクザのヒロイズム」をひどく嫌っていましたが、当時新人だった初タッグの三船の魅力に大きく引っ張られ、その野生的な輝きを際立たせてしまった。でもだからといって、本作を「ヤクザ映画」に分類することはないでしょう。
森:同じく黒澤が監督し、三船と志村喬が出演する刑事映画『野良犬』(1949年 / 東宝)にもヤクザは出てきます。単純に犯罪映画の一種として、あるいは「和製ギャング映画」として捉えると収拾がつかなくなるほど広くなってしまいますよね。
轟:はい。ただその一方で、あえてそこまで含めてみる考え方も面白い気がするんですよ。というのは、のちに三船敏郎は東映のヤクザ映画にも参加するじゃないですか。
森:中島貞夫監督の『日本の首領 野望篇』(1977年)や『日本の首領 完結編』(1978年)に大物ヤクザ役で出演しますね。ヤクザ映画に影響された作品や関連作品なども含めると、本当に多くの枝葉があるわけですね。
ヤクザだけどヒーロー。任侠映画にある、偉大なる定型パターン
森:任侠映画には一定の様式がありますよね。先ほど「ヤクザのヒロイズム」という言葉が轟さんから出たように、任侠映画の主人公はあくまでヒーローなんです。イリーガルなヤクザの世界であっても、主人公は秩序や正しさといった価値観を重んじている。
轟:そうですね。主人公は昔気質のヤクザで、曲がったことが嫌い。物事の道理、筋道を重んじる男です。そこに新興勢力のヤクザがやって来て、その道理を破ってまでも私利私欲を満たそうとする。それに抵抗して、主人公が単身で怒りを持って立ち上がる。こうしたストーリーが最もベーシックな任侠映画の構図になりますかね。
森:時代設定としては明治から昭和初期にかけて(19世紀後半〜20世紀前半頃)……つまり新旧の価値観がぶつかり合う戦前の近代日本が舞台になることが多い。ヤクザという旧世界の側に主人公が居て、そのコードやルールを掻き乱す資本主義的な新世界の悪人の横暴さや薄汚さに怒りを燃やす。構造としては極めて古典的なドラマツルギーです。
轟:わかりやすい二項対立が核にありますよね。当時、任侠路線を立ち上げた撮影所の所長で、のちに東映の名物社長となる岡田茂さんは、亡き主君のために復讐を成し遂げた義理堅い武士たちの物語、日本の古典『忠臣蔵』をモデルに任侠映画を構想したと語っていますから。
外部からの抑圧に対して主人公が「耐える」点も、大衆に支持される典型的な特徴です。主人公は理不尽な仕打ちにギリギリまで耐えて、もう我慢の限界だ、となった最後の段階で暴力を行使する。暴力に正当性を持たせるために、「ここまで耐えたのなら仕方ない」と観客を納得させる「お約束」として機能していたんです。
森:偉大なるワンパターンですね。その定番のストーリーを、いろんなスタッフ、キャストの座組みで繰り返し制作して、どんどん新作を公開していったのが任侠映画です。
定番の型から進歩。複雑化した任侠映画
轟:そうしたジャンルの決まり事って、ブルースやロックンロールにおけるスリーコードのようなものだと思うんです。1960年代の任侠映画の観客は、予定調和も含め、定番となった娯楽映画の黄金律の快感に酔い痴れたのだと想像します。
森:映画の量産体制を可能にした撮影所のシステムからは、多くのプログラムピクチャーが生まれました。アメリカ映画でいうところの「B級映画」ですね。2本立て興行のためにつくられる低予算のジャンル映画、というのが基本の枠組みです。
ただし撮影所があった時代の後半になると、「義理人情に駆られたヤクザが己の命をかけて宿命的な決断を下す因縁劇」という同じパターンを何度も繰り返すうちに、複雑なニュアンスを帯びた作品が生まれてきた。
轟:比較的早い時期でいうと、加藤泰監督の『明治侠客伝 三代目襲名』(1965年)がそうですね。鶴田浩二という大スターの硬派な色気を最大限に活かした傑作ですが、任侠映画の定番とはちょっと違う。
それまで、このジャンルは基本的に「男の世界」を描くものでした。しかし本作は、藤純子(現・富司純子)演ずるヒロイン、娼妓が大きく物語に絡んできて、主人公は義理と恋情の間で心が揺れる。遊郭で身請けされそうになった女に「連れて逃げてくれ」とすがられるも、男は立場上、組を継いで三代目を襲名しなければならない。「いまのわいはなぁ、わいであって、わいでないねん」という主人公の名台詞が象徴的です。単純な二項対立を超えた個人の葛藤を、任侠映画の形式のなかで描いているのが、卓抜なんですよね。
森:反語的な言葉づかいは、まるでシェイクスピアのようです。宿命的な因縁劇としての任侠映画は、突き詰めると神話的な構造美が備わることがある。例えば日本文学の一時代を象徴する作家である三島由紀夫(1925〜1970)は、鶴田浩二主演、山下耕作監督の『博奕打ち 総長賭博』(1968年)を「ギリシャ悲劇のようだ」と絶賛しました。
身内同士が敵味方に分かれて激しく争うことになるドラマを「男の世界」――つまり男同士の情愛を核にして描き切ったのが、性規範や同性愛に関する表象を描いてきた三島の心を特に打った点だと想像できます。おそらく『明治侠客伝 三代目襲名』や『博奕打ち 総長賭博』が公開された時期が、任侠映画のピークであり、その後、ヤクザ映画は次のモードに移行する時期に差し掛かってきます。
轟:そうですね。ここでちょっと、任侠映画の全盛期において最大のアイコンとなった俳優として、高倉健に触れておきたいです。先ほど森さんが挙げられた『人生劇場 飛車角』では準主役として登場し、『日本侠客伝』シリーズ(1964年~1971年)や『昭和残侠伝』シリーズ(1965年~1972年)といった主演作で東映の看板スターになりました。
デビューしてからしばらく、若き日の高倉健は、主役は張ってもどこか無骨さが目立ち、お客の人気を得られない存在でしたが、任侠映画が始まってからは、特にマキノ雅弘監督の指導によって飛翔しました。子役上がりのマキノは、「日本映画の父」と呼ばれた牧野省三の血を受け継いでおり、幼い頃から撮影所で育まれ、つくり手になってからは数々の時代劇をヒットさせ、エンタメの世界の裏も表も知り尽くした「映画づくりの匠」のような存在です。
そんなマキノが好んだ「いなせ」――情に厚く、粋でまっすぐな漢の生き方を高倉は、あるときは市井の職人気質を通し、またあるときは凛とした着流し姿でもって体現した。任侠映画の正道とは、この「マキノイズム」の拡張、あるいは追究といえるでしょう。そしてそれは、日本映画界が黎明期から積み重ねてきた理念や技術の純粋な結晶でもあったわけです。
ヒーローだったヤクザはアンチヒーローへ。ヤクザ映画の大きな転換点
森:『博奕打ち 総長賭博』が公開された1968年は「政治の季節」ですよね。アメリカではベトナム反戦運動、フランスでは五月革命があり、日本でも日米安全保障条約に反対する運動・安保闘争が尖鋭化していく。そうした時代状況が暗に、ヤクザ映画の内容にも反映されていきますね。

轟:それに呼応するように、クライマックスで斬り込みに行く高倉健の姿に、政治運動に身を投じる学生たちが自分の心情を重ねて映画館で熱狂していました。
ただ先ほども話題に出たように、任侠映画の構造は古典的です。だから、そこで謳われるヒロイズムと現実のあいだに、だんだんズレが生じてくる。「いなせ」という男の美学が、偶像視されすぎたロマンとして空転していく。時代が進むにつれて、任侠映画はヤクザをあまりに理想化して描いているのではないか、という疑念がつくり手にも観客にも湧いてきたのでしょうね。
森:個人と組織のあいだの信頼関係があるからこそ、組織を裏切らない「義理」や自分の損得を優先しない「いなせ」という価値観が重んじられていました。しかし、それが信じられなくなる時代が到来したのですね。その結果、任侠映画が徐々に行き詰まりを見せます。
そして、「政治の季節」もピークアウトした段階で、東映は実際のヤクザの抗争をドキュメンタリーに近い質感で描く「実録路線」――実録ヤクザ映画をスタートさせます。一大モニュメントとなったのは深作欣二監督の『仁義なき戦い』(1973年)ですが、この作品が生まれる直前にも、過渡期的な傑作がありますよね。
轟:そのなかでも重要な作品が、実録路線のプロトタイプといえる『現代やくざ』シリーズ(1969年~1972年)です。すべて、主演を務めていたのは、菅原文太。彼こそが、任侠映画で活躍した鶴田浩二や高倉健に替わる新しいヤクザ映画のアイコンになる。『現代やくざ 血桜三兄弟』(1971年)の中島貞夫監督や、『現代やくざ 人斬り与太』(1972年)の深作欣二監督らの作品に出演し、実録路線の立役者となっていくんですね。
森:『現代やくざ』シリーズ最終作の『現代やくざ 人斬り与太』は、同じ深作欣二監督と菅原文太主演のタッグで『人斬り与太 狂犬三兄弟』(1972年)という別の作品へと発展する。そして、このタッグは続いて、まるでホップ、ステップ、ジャンプのように『仁義なき戦い』という決定的な金字塔を生み出します。
同じ時期にハリウッドでは『俺たちに明日はない』(1967年)や『イージーライダー』(1969年)など、アンチヒーローの主人公が特徴であるアメリカンニューシネマの時代に突入していました。日本でも、ヤクザがヒーローから、アンチヒーローとして描かれる時代に移行していく。
轟:そう。極めて破滅的であったり、より生々しく人間の欲望を露わにし、のたうち回るアウトローたちが主人公になりますよね。そのほうが、当時の観客の気分をリアルに託しやすくなってきたということでしょう。先に挙げた『明治侠客伝 三代目襲名』の台詞「わいであって、わいでないねん」に擬えるなら、自己否定の向こう側にあらためて浮上する「……でも、わいなんだ」というアイデンティティーの物語になっていくわけですね。
東映以外の会社の作品にも注目。「ヤクザ映画」に近い作品たち
森:少し角度を変えましょう。1960年代に生まれた東映の任侠路線と並行して、これに類する映画が他の映画会社からも続々と公開されていきましたね。
轟:ええ。各映画会社(松竹、東宝、大映、東映、日活、新東宝)の競争意識が影響を与え合いながら、ジャンルを盛り上げていったのがヤクザ映画の面白さでもあります。
女侠ものに類する映画の製作でいうと、新東宝が一番早いですよね。田口哲監督の『女王蜂』(1958年)や石井輝男監督の『女王蜂の怒り』(1958年)など、一家を構えた親分の娘が跡取りとなり、久保菜穂子が着流し姿で体を張るアクション映画群は、大映で江波杏子が人気を得た『女賭博師』シリーズ(1966年~1971年)や、藤純子主演の東映ドル箱映画『緋牡丹博徒』シリーズ(1968年~1972年)の先駆といえるかもしれません。
轟:男優スターにも目を移せば、日活では高橋英樹が『男の紋章』シリーズ(1963年~1965年)で頭角を現し、西部劇タッチのアクション映画で活躍していた小林旭も『関東遊侠伝』(1963年)以降、本格的に着流しの任俠キャラを演じるようになる。大映には市川雷蔵の『若親分』シリーズ(1965年~1967年)があり、松竹には元ヤクザの組長という経歴の安藤昇が参入……と、とにかく各社が当ジャンルでしのぎを削っていました。
森:例えば過去何度も各社で映画化された長編小説に、港湾の荷役労働者から地元の名士となった実父の生涯を綴った火野葦平の『花と竜』がありますが、最初は1954年に東映が手がけていますよね。
轟:主演は藤田進で、監督は佐伯清。のちに高倉健主演の『昭和残侠伝』シリーズの生みの親になります。
森:その次が日活で、意外にも『人生劇場 飛車角』より早く1962年の年末に石原裕次郎主演、舛田利雄監督でつくられているのが興味深い。
ところで同じ裕次郎主演、舛田監督のコンビでいえば、『赤い波止場』(1958年)という「和製ギャング映画」があります。これは舛田監督自身の手によって、渡哲也主演の『紅の流れ星』(1967年)にセルフリメイクされる。この作品では『望郷』(1937年)や『勝手にしやがれ』(1959年)といった、フランス映画の名シーンが露骨に参照されています。
そのほか、宍戸錠主演、野村孝監督の『拳銃(コルト)は俺のパスポート』(1967年)など、欧米の雰囲気を模倣したスタイルの和製ギャング映画が日活アクション映画の中から登場します。
轟:当時の日活は他社同様、アメリカ映画やフランス映画の味わいを自分たちなりに翻案しようとしていた。ただしその結果は、ワールドワイドというより──「日活無国籍アクション」という呼称もあったように──格別にユニークな独自性を確立する成果へとつながりました。制作陣の技術が非常に高く、いま観ても面白い作品が多いですね。
逆に日本から欧米への影響について考えると、フランスのノワール映画の名手であるジャン=ピエール・メルヴィル監督は日本の美学を自身の作品に援用しており、有名なところでは『サムライ』(1967年)があります。原題が『Le Samouraï』で、開幕早々、書物『武士道』から引用した一節として「サムライの孤独ほど深いものはない。さらに深い孤独があるとすれば、ジャングルに生きる虎のそれだけだ」と記されるのですけれど、新渡戸稲造の原典とは関係なく、完全なるメルヴィルの創作(笑)。にもかかわず演出や撮影、美術と隅々まで武士道精神を感じさせる厳かな雰囲気がみなぎっていて素晴らしい。
森:当時は映画会社ごとに、それぞれ作品のカラーがありました。東宝はモダンな作風が多い。岡本喜八監督は『暗黒街の顔役』(1959年)、『暗黒街の対決』(1960年)という和製ギャング映画を撮っていて、前者は鶴田浩二の主演、後者は三船敏郎と鶴田のW主演です。
松竹では、日本国民の間でとてもポピュラーな人情喜劇、山田洋次監督の『男はつらいよ』シリーズが1969年に始まります。これもヤクザ映画から派生した作品の一種かもしれない。渥美清演じる主人公の「寅さん」こと車寅次郎は、流れ者のテキ屋(露店などで行商を行う業者で、ヤクザの一種として定義される)ですから。
轟:このシリーズの始まりを、ヤクザ映画のパロディーだと評する人もいますよね。ぼくは、つくり手側にパロディーの意図は薄いように思います。むしろヤクザ者になろうとしてなりきれず、故郷に戻ってはついつい小市民的な幸福を求めてしまう二律背反が、シリーズの主人公である寅次郎の本質なのかもしれません。
寅次郎のニックネームは「フーテンの寅」。「フーテン」とは漢字で書けば「瘋癲」で風来坊的な意味合いですが、日本版ヒッピーの文脈に組み込むこともできます。アメリカでもヒッピーが全盛期を迎えた1969年という時代を反映したキャラクターであったとも考えられるでしょう。
また松竹では、最終的には会社を飛び出す大島渚や吉田喜重らが活躍し、新たな映画表現を試みた「松竹ヌーベル・バーグ」と呼ばれるムーブメントがありました。その旗手の一人である篠田正浩監督は、非常にスタイリッシュなノワール映画『乾いた花』(1964年)で一匹狼のヤクザを魅力的に描き出しました。これを演じていた池部良は、東映の『昭和残侠伝』シリーズで高倉健の相棒役に起用され、毎回大人気を集めました。こういう会社やジャンルを跨がった影響関係も見逃せないところだと思います。
『仁義なき戦い』をはじめ東映「実録路線」以降、現代までの作品について解説する後編はこちら。
轟夕起夫(とどろき ゆきお)
映画文筆家。1963年東京都生まれ。『キネマ旬報』『映画秘宝』『クイック・ジャパン』『DVD&ブルーレイでーた』『QJweb』などで執筆中。近著(編著・執筆協力)に、『伝説の映画美術監督たち×種田陽平』(スペースシャワーブックス)、『寅さん語録』(ぴあ)、『冒険監督』(ぱる出版)など。
森直人(もり なおと)
映画評論家、ライター。1971年和歌山生まれ。著書に『シネマ・ガレージ~廃墟のなかの子供たち~』(フィルムアート社)、編著に『21世紀/シネマX』(フィルムアート社)、『ゼロ年代+の映画』(河出書房新社)ほか。