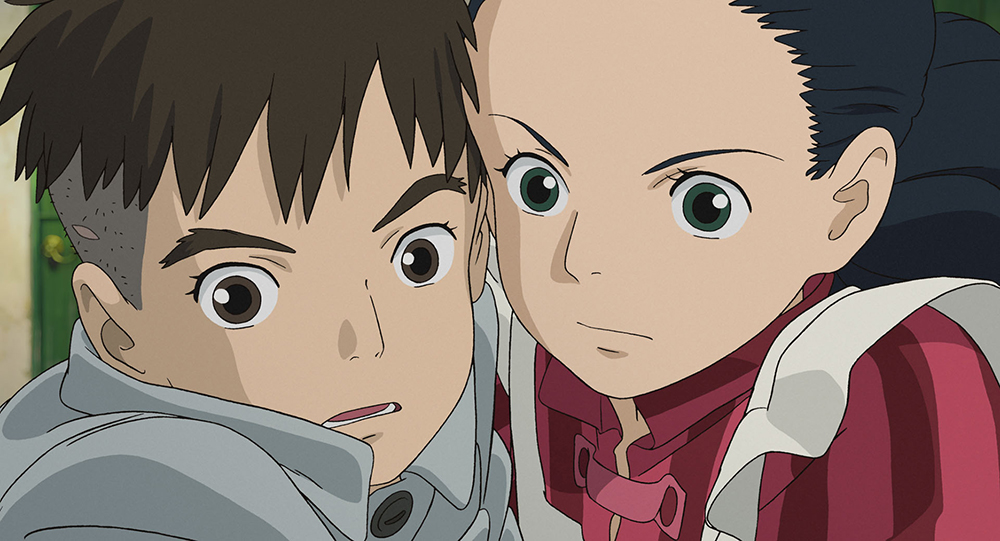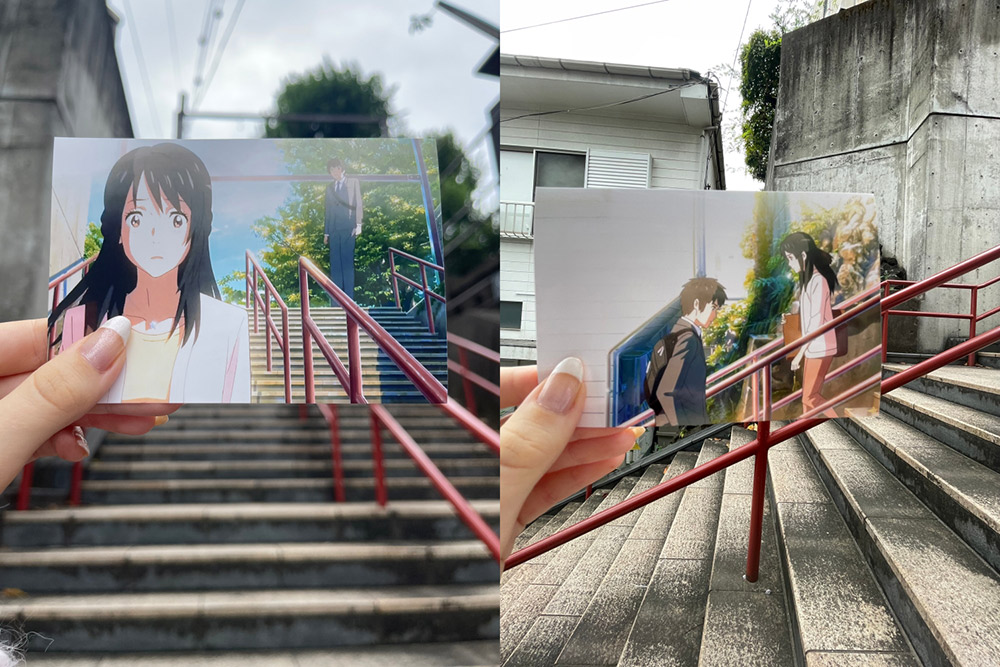世界中のファンを魅了する日本のアニメ。音響監督は、アフレコ、効果音、BGMなど作中の音に関わるすべての制作をリードする役回りだ。三間雅文氏は、1988年に音響監督としてデビューしたあと、アニメ『ポケットモンスター』シリーズや『進撃の巨人』など、多くの作品で辣腕を振るってきた。三間氏は、自身の仕事を「監督の通訳」と説明するが、どのようにして作品に魂を吹き込んできたのだろうか。
取材・文:嘉島唯 写真:丹野雄二 編集:森谷美穂(CINRA, Inc.)
ジブリ映画の現場を見て、「音響監督」の真髄を理解した
——「音響監督」という仕事は日本にしかないそうですね。
三間:はい。だからなのか、海外のファンの方からは、自分の仕事は作曲家さんとかミキサーさん(機材を用いてセリフやBGMなどの音量バランスを調整する技術者)だと誤解されることが多いです。
音響監督の仕事は、人によって多少異なる部分もありますが、僕は役者の台詞、音楽、効果音など、作中に出てくるあらゆる「音」に携わります。監督が思い描く世界を音で表現するにはどうしたらいいか、それを考えて、声優さんや作曲家さんなどの方々に伝える、いわば「通訳」みたいなものです。具体的には、芝居のディレクションや楽曲の選曲、またそれらの音をどう組み合わせて聞かせるかを検討しています。

三間:自分のキャリアは、明田川進さん(※)が経営しているアニメの音響会社に誘ってもらったことからスタートしましたが、当時はまだ音響監督の仕事内容が曖昧でした。最初の仕事は1983年に開園した東京ディズニーランドのオープン前夜祭でのアシスタントでしたからね(笑)。
——「音響監督の仕事」の真髄を理解したのはいつ頃でしたか?
三間:独立したときでしょうか。その頃にスタジオジブリ映画『風の谷のナウシカ』(1984)『天空の城ラピュタ』(1986)で音響監督を務めた斯波重治さん、『機動戦士ガンダム』(1981)『エルマーの冒険』(1997)の松浦典良さん、テレビアニメ『ドラゴンボール超』『ちびまる子ちゃん』シリーズの本田保則さんの現場を見学させてもらったんですね。
三者三様、異なる仕事ぶりを目の当たりにしたときに「音響監督という山の頂は高い」と痛感しました。なかでも衝撃を受けたのは、斯波さんの現場です。斯波さんはご自身が演者だったこともあって、監督よりも芝居の本質を理解されていた。「この役はいまこういう気持ちだから」と説明する姿を見て、自分が目指す「音響監督像」がわかったような気がします。
音楽は感情の流れを描くのに効果的です。ただ、芝居に感情がしっかりと乗っていれば音楽はいらない。まずは芝居に注力し、補足が必要な場合に音楽や効果音を入れることで、作品の完成度が上がっていくと考えています。
(※)明田川進:日本のアニメ黎明期から音響監督としてアニメに携わる。主な作品は『リボンの騎士』(1967〜1968)『AKIRA』(1988)など

絶叫アトラクションに乗って「重力に耐える声」を特訓
——三間さんはどんな風にお芝居のディレクションをしてきたのでしょうか?
三間:僕は、芝居が嘘にならないことが大切だと思っています。そのために、演者には「なるべく原作を読まないで」とお願いしています。それは、例えば「明日死ぬ」とか、未来がわかっている人なんていないからです。死ぬことを知らないからこそ、殺されるとき、死ぬほど驚き、苦しむ。
また、オリジナルビデオアニメ『マクロスプラス』の主人公・イサム・ダイソンがG(重力)に耐えるシーンでは、河森監督のアイディアで、実際に遊園地へ行き、垂直方向に急降下する絶叫アトラクションに演者さんと乗って重力を体感しながら台詞の練習をしました。
——演者さんが実際に体験することで、迫真のお芝居につながるのですね。
三間:録音の際に声そのものを加工して、求めている音をつくり出すこともあります。例えば、『鋼の錬金術師』シリーズに出てくるアルフォンスは、声で鎧姿の雰囲気を出すのに苦心しました。スタジオの機材で録音後の声を加工することも可能ではあるものの、独自のエフェクトが欲しかった。Amazonを見ていたら、セサミストリートに出てくるようなアルミ製の大きなゴミ箱が売っていたので「これだ」と。ゴミ箱に穴をあけ、スピーカーを入れて録音しました。
——長く携わっているアニメ『ポケットモンスター』では、どのようにお芝居と向き合っているのですか? ピカチュウの「ピカ!」というセリフにも、一つひとつ意味があると聞いたことがあります。
三間:はい。アニメの台本では「ピカ!」の下にピカチュウが何を話しているのかを書いてもらっています。主人公のサトシが「行くぞ、ピカチュウ」と言ったときに「えー、僕も?」なのか「やるぞ!」なのかでは、鳴き声が全然違いますよね。ポケモンもしゃべっているんです。
三間:ピカチュウが登場するCMなどの現場では、僕はピカチュウの「飼育員」としてアフレコに参加しています(笑)。台本が「ピカ!」としか書いてなかった際に、制作側がピカチュウ役の声優さんに、どのような気持ちで言ってほしいのかを伝えるのが僕の仕事。挨拶してほしいのか、自己紹介する場面なのか。「ピカ!」には状況によっていろいろな気持ちがのっています。
失神するほど無我夢中だった、今敏監督の現場
——妥協しない姿勢は、誰からの影響が強いと思いますか?
三間:忍耐力という面では、今さん(今敏監督)の存在が大きいように思います。僕は、監督デビュー作の『PERFECT BLUE』(1998)から一緒にやらせてもらったのですが、今さんは労力度外視で作品に向き合い、凄まじい勢いで進化していく監督でした。
三間:初めは「新人監督さんです」と紹介されて、ご本人も「音に関しては素人なのでわからない」と口にしていたのに、すぐ「選曲してきました」「効果音はこういう音にしたいです」と攻めの姿勢になった。
今さんは、エイリアンのような人でした。エイリアンは銃で攻撃すると、その銃をコピーして撃ってくる存在でしょう? こちらが持っている武器を吸収して、さらに強くして返してくる。
だからこそ、いつか「音響監督はいらないです」と宣告されそうで怖かった。『千年女優』(2001)では、エレベーターのドアが開いた瞬間、ラジカセが大音量で鳴るシーンがあるのですが、普通だったら音が割れない程度の音量にするところを僕は「あえて音が歪むぐらいにしましょう。そのほうが不気味さを出せます」と提案するなど、なんとか今さんに面白がってもらおうと必死でした。
三間:今さんは、すごく丁寧な方なので、嫌う人なんていなかったと思います。完成した作品は芸術の域に達する美しさがあり、本当に報われる。けれども、作品を重ねるごとに僕の神経は極限まですり減っていきました。現場には底知れない重圧があったんだと思います。
『パプリカ』(2006)のアフレコが終わり、ミックス作業のときに僕は現場で寝落ちしてしまいました。あとになって今さんから「最後のほう、三間さんはぐったりしていて、困りました」と怒られました。僕は、その場で謝罪をしたものの、「もう無理だ」と……。今さんからは「次も三間さんと組みたい」と言ってもらえましたが、「頑張ります」と言えませんでした。倒れるほどやり切ってしまったので、それ以上の力で応えることはできないと思ったんです。

三間:そのときは、まさか今さんが亡くなるなんて思っていなかった。今さんの遺書には「お先に」と書いてあって、その文字を見て号泣しました。僕は最終的に今さんから逃げたのだと。悔いと罪悪感が心に残っています。
『進撃の巨人』の制作現場で感じた懐かしさ
——『パプリカ』のあと、2013年から三間監督はアニメ『進撃の巨人』を担当しました。巨人と人類との戦いを描き社会現象を巻き起こしたといわれる作品ですが、制作にあたりどのような苦労があったのでしょうか。
三間:巨人という存在を音で表現するのには苦労しましたね。同じ背丈の人を見るときと、60メートル級の巨人を見上げるときの声は絶対に違いますし、平和な日常が突如壊されて極限状態に陥る芝居のオーダーも難しかったです。でも、一言で恐怖が伝わりさえすれば、視聴者は「ながら見」ではなく、画面に集中せざるを得なくなる。
映画館では「見る」ことに集中してもらえますが、家で見る場合は途中でやめられるし、スマホをいじりながら見ることができます。そのため、『進撃の巨人』は音を使っていかに注意を引けるかを意識していました。
例えば、物語のクライマックスにあたる「The Final Season」では、アルミンが飛行艇のドアを開けた瞬間、耳鳴りの音だけがして、無音が訪れる。そして、アルミンが主人公の名前を呼んだあとで初めて音楽が流れます。林監督からアイディアをもらい、没入感をつくるために「静と動」のコントラストを強め、微調整を繰り返し、監督にプレゼンしては改善していきました。
——まさに「通訳」として監督と二人三脚で作品をつくり上げていたのですね。
三間:3期まで監督を務めた荒木哲郎監督は「なぜこの演出なのか」という自問を繰り返しながら作品を追求していく方で、今さんと同じ匂いがしました。とても似ているんです。とにかく「できない」と言わないチームで、妥協は一切ありませんでした。
例えば、3期12話のエンディングで行なった、エンディング曲が流れている途中で突然画面と音が乱れる仕掛けでは、スローになる部分で「いろいろな台詞を重ねて、早回しにしていくのはどうですか」とサンプルをつくり、荒木監督とブラッシュアップしてきました。あの数十秒を2、3時間かけてつくっています。
思えば、荒木監督とは本気の対決ばかりしていました。選曲のラインナップをお互いに見せあって「ここはいいね」と話したはずなのに、蓋を開けてみたら僕の選曲が一曲もないことも多かったです。なので「今回は一曲の変更もありません」と言われたときは、死ぬほど嬉しかった。
頂はまだ高い。『THE FIRST SLAM DUNK』の衝撃
——今さんとの辛い別れのあとで『進撃の巨人』を走りきり、バーンアウトはしなかったのでしょうか?
三間:荒木さんが『進撃の巨人』の監督を降りる際、本当は僕もやめようと思っていたんです。でも「三間さんは絶対に残ってください」と言われて、最後まで走り切りました。60歳で引退しようとも考えていたのですが、『進撃の巨人』の途中で還暦を迎えて、いまも別の作品をつくり続けている。結局まだ現場に出ています。
——現場に立ち続ける背景には何があるのでしょうか?
三間:『THE FIRST SLAM DUNK』(2022)を公開初日に観に行って、衝撃を受けたんです。バスケットボールの一試合を全編かけて描く本作ですが、特に悔しかったのは、試合の途中に挟まるメンバー達のモノローグの描き方。現実の体育館内の音が、まるで水中にいるようにぼんやりと聞こえていて、そこにモノローグが入っていきます。自らの精神世界に沈んでいくようなキャラクターの心情が、音で見事に表現されていて、「やられた!」と思いました。
自分も似たような演出をしたことがあるのですが、ここまで完璧にできなかった。それも、総監督としてこの演出をやってのけたのは、本業は漫画家である原作者の井上雄彦さん。脱帽しましたね。こういう作品と出会えると、もっと高い頂を見たいと思ってしまうのです。

三間雅文
日本アニメの音響監督。音響制作会社・テクノサウンド代表。1989年にアニメ『ドラゴン・クエスト』でテレビシリーズの音響監督としてデビューし、『ポケットモンスター』『進撃の巨人』『PERFECT BLUE』などのアニメ作品を手がける。Netflixで配信中の、『鉄腕アトム』の一部をリメイクしてつくられた浦沢直樹原作のアニメ『PLUTO』にも携わっている。