「1970年代から今日まで続く日本の〈アートハウス〉は、ミニシアターという呼称で親しまれてきました」——コロナ禍真っ只中の2021年1月に始まったイベント『現代アートハウス入門』の説明文には、このように書かれている。
ビクトル・エリセ、ヴィターリー・カネフスキー、エリック・ロメール、ロバート・フラハティ……劇映画からドキュメンタリーまで、古今東西の名作を日本全国のスクリーンで上映してきた同イベント。作品を観たあとは、濱口竜介ら現役の映画作家や研究者、俳優などによって作品に関するレクチャーを受けられる「講座」の時間が設けられるのも特徴だ。
日本における「ミニシアター」の歴史を踏まえながらも、既存のイベントにはない新鮮なアプローチをとった同企画。キュレーターを務めた配給会社「東風」 の渡辺祐一氏に話を聞くと、その視座からは、これまでとは微妙に異なるかたちでの文化発展の可能性と、そのための課題が浮かびあがった。
取材・文:宮田文久 撮影:苅部太郎 編集:井戸沼紀美
「ミニシアター」を同時代的な場として提示するコロナ禍の新企画
——ここ2年ほど映画ファンのあいだで話題になってきた『現代アートハウス入門』ですが、どのように始まったのでしょうか。
渡辺:2021年1月30日から2月5日にかけて、『現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜』というイベントを開催したのが最初です。
ビクトル・エリセ監督の『ミツバチのささやき』(1973)やフレデリック・ワイズマン監督の『チチカット・フォーリーズ』(1967)など、「ミニシアター」と呼ばれる日本のアートハウスを彩ってきた作品を「ネオクラシック」(=新しい古典)という呼び方のもとに集め、それらを全国18の映画館で同時刻に、7日間連続で日替わりに上映しました。
上映後には「講座」として、2000年以降にデビューした映画作家の皆さんや研究者、俳優などに、作品の魅力や自身への影響についてお話いただいたんです。この様子は全国18のスクリーンに生中継し、各劇場の観客から質問を受けつけるQ&Aも実施しました。

——日本では「ミニシアター」という愛称で親しまれている単館系の映画館ですが、今回のイベントで、むしろ海外で一般的な「アートハウス」という呼称を用いた理由は何ですか。
渡辺:日本でミニシアターがはたしてきた役割を振り返ると、もちろん刺激的な作品と観客が出会う場という意義が大きいわけです。しかし既存の「ミニシアター」のイメージを回顧的に反復しながら単に名作上映のような企画を組んでしまうと、その存在がとてもスタティック(静的)なものに見えてしまう懸念があります。
今回は海外のコンテクストに接続できる「アートハウス」という呼称を選びつつ、オリジナルの「講座」をセットにすることで、「ミニシアター」がダイナミックで生々しい場であることを若く新しい観客と共有したいと考えました。上映される作品に新しいコンテクストを与えてくれることも、ミニシアターの重要な役割の一つだと思います。
——『現代アートハウス入門』はコロナ禍にみまわれて映画館や配給会社の経営が苦しい時期に立ち上げられた企画です。にもかかわらず熱心な観客を集め、注目を浴びました。
渡辺:もうひとりのキュレーターである配給会社gnome(ノーム)の村田悦子さんやユーロスペース支配人の北條誠人さんをはじめとして、多くの方々との協働なしには実現しなかった企画です。
ミニシアターのほとんどが独立した資本によって運営されていて、それぞれ独自のプログラムを組んでいます。しかし今回はコロナ禍での危機感を共有していたからこそ、18館もの劇場で一斉に同じ作品を上映するという企画を実現できたのだと思います。講座に登壇いただいたゲストの方々も、そうした状況を理解して協力してくださいました。
——独立しながらの連帯があったわけですね。
渡辺:2021年初頭ごろは世の中が災害ユートピア*のようになっていて、「劇場に行くことが文化を支えることにつながる」という意識があったようにも思います。
そうした背景もあってか、『現代アートハウス入門』にはたくさんの若い観客が駆けつけてくださいました。熱心にメモをとりながら観る方もいれば、短い会期のなかで何度も顔を合わせる方もいました。企画側としても、劇場の方にとっても、これは本当に嬉しいこと。ぼく自身、心が追い込まれていたあの時期においては、精神衛生的にもよい体験だったんです。
*アメリカの著述家レベッカ・ソルニットによって広く普及したとされる概念。大規模な災害の後で一時的に人々が手を差し伸べあう状態を指す

正解や常識にとらわれない映画の楽しみ方を
——さまざまな上映と講義が行なわれた初回開催を受け、同年の12月には『現代アートハウス入門』の第2弾が、翌年10月には第3弾が開催されています。第一弾と第二弾ではフィクションとドキュメンタリーの両方を紹介していましたが、第三弾は少し趣が異なりますね。
渡辺:第3回は「ドキュメンタリーの誘惑」という副題のもと実施しました。まず、小田香監督や深田晃司監督など、日本の18人の映画作家に「若く新しい観客に映画の魅力を伝える5本の『ドキュメンタリー』を観せるとしたら?」というアンケートにご協力いただき、その結果をウェブ上で発表したんです。

渡辺:後日、そのリストのなかからロバート・フラハティ監督の『ルイジアナ物語』(1948年)や佐藤真監督の『SELF AND OTHERS』(2000年)など7本の映画をセレクトし、プログラムを組んで、全国5か所の劇場で巡回上映を行ないました。第1弾、第2弾のようにレクチャーの中継はしませんでしたし、上映館の規模も縮小しています。
ただ第3弾では、大阪のシネ・ヌーヴォや鳥取のjig theaterなど、各地方の劇場でゲストを招き、トークショーを実施しました。そのことによって「東京からの発信」ではないかたちを模索できた意義は大きかったと思います。

——このイベントの特徴でもある「講座」は、それぞれどのような雰囲気で行なわれていたのでしょうか?
渡辺:ゲストの方たちが、柔らかい雰囲気のもとでお客さんたちを迎え入れて、一緒にスクリーンを観るような語り口で話してくれたことが、とても印象的でした。
なかでも『ミツバチのささやき』上映後の講義で、濱口竜介監督が「学生時代、同作を初めて見たときは寝てしまった」という話をしたとき、会場全体が不思議な安堵感に包まれたことをよく覚えています(笑)。
最初はどう観ていいのかよくわからない作品でも、画面の肌理や手触りから何か感じられるものがあれば、それだけでも映画というものは面白いと思うんです。
——『ミツバチ』の回では、観客からまるで「恋バナ」のような質問が出たとも聞きました。
渡辺:ありましたね! 「好きな人に『ミツバチのささやき』を勧めるとしたら、どんな勧め方をしますか」というような質問だったかと思います。講師の皆さんは少し照れながら、けれど、ずいぶん真摯に答えてくださいました(笑)。
『現代アートハウス入門』の第1弾と第2弾では、ウェブ上の投稿フォームを利用して、全国の参加劇場のお客さんから一斉に、登壇者への質問を集めたんです。そうした形式をとったことで、観客が挙手をして質問する、というかたちではなかなか出てこないような、本当に多様な問いが寄せられました。「正解を知る人間が壇上にいて、それをオーディエンスが聴く」という構図から、すこし解放されたような気がしています。

複雑な現状を複雑なままにとらえることの大切さ
——イベントを実施したことで見えてきた今後の課題はありますか。
渡辺:『現代アートハウス入門』は、公的な助成があったからこそ実施できた企画です。第1弾から第3弾まで、文化庁の「文化芸術収益力強化事業」や、コロナ禍における補助金事業「ARTS for the future!」を活用することで、それぞれ開催できました。ただ正直に言いますと、これを東風という配給会社の自主事業としてやろうとは、まったく考えていません。
充実したプログラムを組むためには、相応の予算とマンパワーが必要です。無理して行なえば上映作品の配給会社や映画館、ゲストといった関係各位にもしわ寄せがいくことが目に見えているからです。
ミニシアター=アートハウスの社会的・文化的な価値を次世代へつなぐためにも、公的な助成を緊急避難的なものではなく、恒常的なものにしていってほしいと感じています。

——文化の持続性を支えるシステムが求められている、と。
渡辺:もちろん現在も、いくつかの支援や助成の制度は存在しています。しかし現状にはまだまだ改善の余地があると感じるからこそ、こうしたお話をしている次第です。
ぼくは市民講座や大学の講義などで、映画に対する公的な助成について受講生たちとディスカッションすることがあります。印象的なのは、映画制作に対する支援については了解され、映画館に対する支援も受け入れられるのに対し、配給会社に対する支援は「ビジネスだから公的な助成は要らないでしょう」という声が多くなることです。
しかし実際にはそれぞれの担い手が、映画が観客に届くまでのひとつのエコシステムを形成しているわけです。こうした実態について社会的な理解を得るにはどうすればいいか、私たち配給会社自身も考えていかなければなりません。
——緊急避難的ではなく恒常的に、点ではなくシステムという面へ……文化の担い手をめぐるとらえ方自体が問われます。
渡辺:仮に、アートハウスと呼ばれるひとつの映画館のことを考えてみましょう。その映画館は、ビジネス面だけを考えて運営されているわけではないでしょうし、かといって文化的な意義だけを信条として運営していけるのかと言われたら、決してそうではない。もっと複雑であり、重層的であるわけです。こうしたさまざまな側面を持っているのは制作に携わる人間でも、配給会社でも同様でしょうし、もっといえば観客だってそうかもしれない。
複雑なことを、複雑なままに、きちんと考えなければいけないところにきているはずだ、と感じます。『現代アートハウス入門』という試みについて知っていただくことが、そのひとつのきっかけになれば嬉しいです。
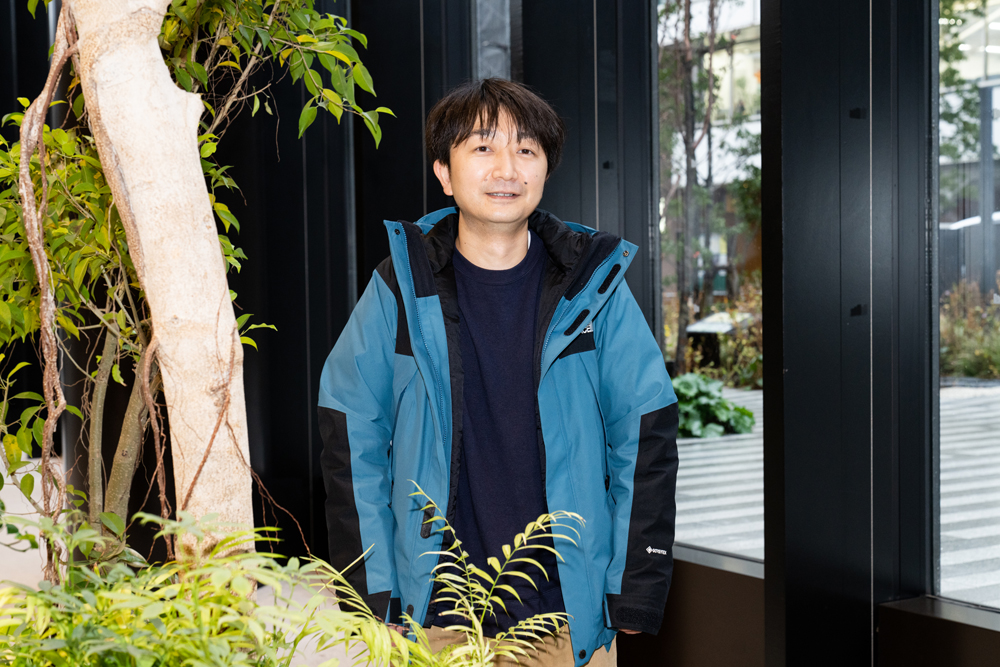
合わせて読みたい:「ミニ」から世界へ ―― 日本のミニシアター文化史
合わせて読みたい:日本映画の多様性を守るために。諏訪敦彦が考える映画業界の未来
渡辺祐一(わたなべ ゆういち)
1978年生まれ。2009年、配給会社東風の立ち上げに参加。以降、同社スタッフとしてドキュメンタリーを中心に映画配給を手がける。2014年より日本映画大学非常勤講師として興行・配給システムを講じる。











